
前回ブログで、
『不器用ルアー 縁(えにし)』
として作る形などが決まったので製作を開始したのだ!
バルサ材の質の違い!
僕はバルサ材を使って、
- セルロースでコーティングして、
- 不器用ルアーを作っている。
なので時々バルサ材を購入している。
バルサ材はホームセンターなどで購入しているが、購入時には注意事項がある。
同じ厚みのバルサ材としてお店に陳列されていても、
並んでいるバルサ材の質は全然違うのだ!
バルサ材だから何でも一緒では無い。
例えば先日久し振りにホームセンターにバルサを買いに行って驚いた。
同じ厚みで並んでいたバルサの質がこれでもかと言うくらい違ったのだ!
↓5枚とも全然違う。
1番色の薄いのと濃いのを並べた。
同じバルサとは思えないくらいだ。
結局この日は買わずに帰宅したのだが僕は田舎の僻地在住である。
- バルサを購入する場所も少ないし、
- 買う人もあまり居ない。
つまりバルサ材の商品の回転も良くない。
なので気を付けないと、
半年前の自分が買わずに見送ったバルサを半年後の自分が買ってしまう事もあるのだ!
(実話です)
バルサ材は数百円で買えるので、
- 値段の安さに油断していると、
- 自分の好みではないバルサや、
- 以前に自分が見送ったバルサ。
そんなものを買ってしまったりする。
しかしここで問題なのがバルサ材の好みは人によって違うのだ。
- これは男性から見る女性の好みが、
- 人によって違うのと似ている。
例えば僕は女性が眼鏡をかけているだけで2割増し可愛く見える。
(いやもっと可愛く見える)
素敵な眼鏡女子がずれた眼鏡を直す仕草なんて見れた日にはスキップで帰宅する。
(良いビールも買って帰りたい)
だけど一方で眼鏡女子に対して何とも思わない男性もいるそうだ。
(僕は信じられない。信じたくない)
同じように人によりバルサ材に対しての好みも違うのだ。
(眼鏡女子の例えはいらなかったかもしれない)
僕はルアー製作初期にフローティングミノーばかり作っていたからか、
- 色が白くて筋も少なくて、
- 柔らかくて軽いバルサ材。
が好みである。
一方で少し硬いバルサが好みの人もいるらしい。
そもそもバルサでは無い木材で作っているルアーもあったりする。
- 有名なウッドリームのアルボルも、
- 素材がバルサのものもあれば、
- ハードウッドというものもある。
↓50㎜シンキングはハードウッド
適材適所とはよく言ったもので、
- 作りたいルアーや、
- 目指すアクション。
- 重視するものの違い。
それによってバルサ材や他の木材の好みは変わるのだと思う。
まあ僕なんかはバルサ材の質の違いにこだわる前に、
- いつも同じ質のルアー。
- それが製作出来るように、
製作の質(腕)を磨くべきではある。
しかし同じように作っても、
- そもそものバルサの材質が違うと、
- 出来上がったルアーは、
- 微妙に違うはずである。
そう思うとバルサ一つとっても奥が深いのである。
バルサ材は通販などでも売っているようだが僕は買った事がない。
ホームセンターで買うから余計に質がバラバラなのでちゃんと見る必要があるのかもしれない。
ルアー製作開始!
製作はルアーの切り出しから始まる。
形は決まっているので同じように切り出していった。
ルアー製作の時にはオルファの細工用カッター(刃先30度)を使っています。
↓これです
ただ切り出すだけなのだがなぜかよく分からない失敗をしてしまったりもする。
下の写真は切り出してから断面をやすった後。
他の器用な方はどうかわからないが、
- 僕の場合はバルサ材の断面を、
- カッターだけで綺麗に切れない。
なので少し大きめに切った後にヤスリがけして平たくならしている。
バルサ材をやすると粉が舞うので外で作業する。
下記は会社の昼休みにやすった。
丁度良い台が外にあったので目星を付けていたのだ。
やすると断面が平らになる。
同じように切ってやすったつもりでも、並べると大きさが少し違ったりする。。。
それからバルサを削って形にしていく。
↓すでに少し違う形のものもある。。。
削って形を出した後のルアーを測ると1番軽くて0.2g、
0.3gもあれば、
1番重いのは0.4gもあった!
↓僕のと同じ0.1gまで。本当は0.01gが欲しい。
僕の好みのバルサ材だけを買っているつもりだがそれでも少しはバラツキがある。
僕の場合はバルサ材の重さの違いはそのまま完成品の重さの違いになったりする。
今回切り出したバルサ材からまずは10個を不器用ルアー 縁(えにし)として製作スタートする。
正直僕の力量では1回の製作量は6個くらいまでが目が行き届きやすい。
だけど失敗という落とし穴が沢山あるので多めに作ってみる。
どれだけちゃんと完成するかもわからないので次のロットも切り出ししようと思う。
とにかく幾つか数を作ってみて、どれだけものになるか。
試作6回目のように不器用ルアー 縁(えにし)として好みの動きになるのは何個出来るだろうか。
このシーズンオフには集中してルアー作りをしたいが、
- 塗装している外の倉庫は冬にはマイナス何度かになるし、
- ルアー作りに集中すると持病のヘルニアが出る可能性もある。
なので早めにいくつか数を作っておきたいのだ。
早めに作りたい気持ちはあるが焦るとロクな事にならない。
不器用ルアーを人に使って貰えるように。
まずは一つずつバルサ材を削ったりやすったりしている僕なのであった。
「たしかに同じバルサ材だと思えないくらい違う!」とブログ応援クリックお願いします(^O^)/↓
![]()
にほんブログ村
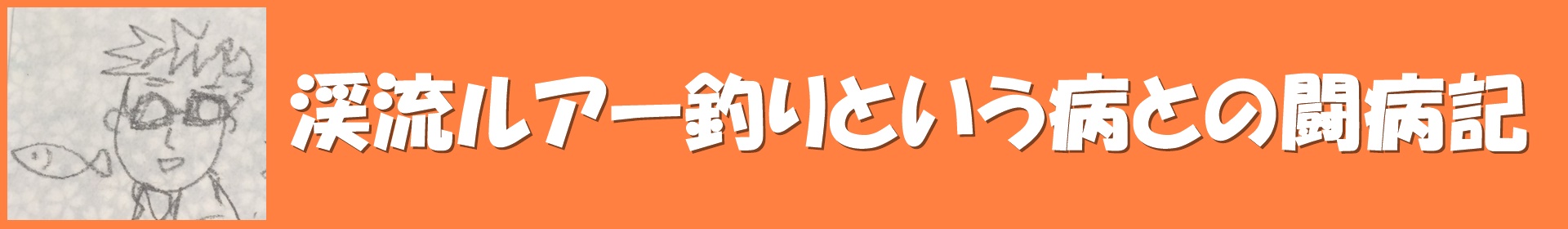
















バルサ材は加工しやすく軽いのがメリットですかね。
そういえば学生時代、モデルを作るのにジェルトン材というバルサよりは硬いけど割と加工しやすい木材よく使ってました。目が細かいので塗装とかの下処理は少なくて済んだから使っていたような。 比重はバルサより重いかと思いますが、ルアー製作で使っている人いるのでしょうか??
カッターでも切り出しやすいバルサですが、厚みのあるものを真っ直ぐな断面にするのは意外と難しいと思います。 仕事でもスチレンボード(厚み6ミリ位)をカッターでカットする事ありますが、大抵は断面は斜めります。 ちゃんとした道具使えばもっと楽に切れると思うんですけど、そこまで精度いる工作ではないので適当ですね(笑) しげるさんが大きめにカットしヤスリがけするのは賢いと思いました。
ハンドメイドの良さは一個づつ個性がある事だと思います。作者の魂が入っているか否か。 楽しみながら思いの丈ぶつけて納得のいくモノ作りしてくださいまし。 失敗は成功の素、いや失礼、偶然が閃きを生み出し、面白いモノが作れると思います。
不器用ルアーは個性的な良い作品だと思っておりますよ(ヨイショ!)
バルサ材は比重が軽くて浮力があるのと加工しやすいのがメリットだと思います(^^)
ジェルトン材というのは初耳です!ルアーに使っている方は僕は知らないです!
きんくまさんも切り出し斜めりますか!
なんだか嬉しいです(^^)
切った後にヤスリがけして平らにするのは時間がかかるのですが失敗は少ないです(^_^)v
ヨイショありがとうございます(^o^)
励みになります(^^)
コツコツ作って見ます(^_^)v
今頃横から失礼します。
40年前に最初期のタックルハウスのツインクルを買いましたが、それがジェルトン材で作られています。(現在のは分かりませんが・・・)
私もその頃からルアー作りはバルサ材ばかり使ってましたが、ツインクルがハードウッドで作られているのを知ってから、ホウやら色々使いましたが、やはり加工が本当に大変でした(笑)
当時のツインクル、ジェルトン材で作られているんですね!
名作ルアーが作られた素材は興味があります!
渓流用ハンドメイドルアーの多くはバルサ材だと思うのですが、ウッドリームさんなど、中にはハードウッドを使われているものもありますよね。
なのでハードウッドが気になってはいるのですが、バルサの加工のしやすさと、ハードウッドの加工のしにくさを考えて手を出せずにいます(^_^;)
ルアー作りは素材やウエイトや色々と考える事が多くて、それが楽しいですね!(^^)!
コメントありがとうございました!
成る程なぁ。用途別に使うバルサの密度を選ぶんですね!。
バルサを使ってルアーを作る時は誰もが高浮力の物を選んで作ってるのかと思ったらそぉではないんですね!?。勉強になりました。
杉からルアー作りを始めたので、初めてバルサ材を使った時は、確かにあの高浮力の素材をシンキングにするのに苦労しました(^^;。まぁ、今でもなんでけどね(苦笑)。
僕もみんなが軽い高浮力のバルサが好みだと思っていたら違うみたいなんです。
少し硬めが好みとか人によってあるみたいです(^^)
いちろーさんは杉からでしたね(^^)
杉からってけっこう珍しいと思います!
でもバルサ以外の木でも渓流ハンドメイドミノーを作られている方もいらっしゃるのでやはり適材適所なんだと思います(^^)
あっその苦労なら僕も今でもしています(^o^)
本当に、どこにでも顔を出す奴だなぁ…
の、ヘルクライマーでございます。
自分もハンドメイドミノーに凝った口ですよ。
.
<第一期>
バスが釣れ始めた中学時代、少ない小遣いを温存する目的で製作を開始。
小学館『きみは釣り名人』の巻末に掲載されていた、
ラトル入りクランクベイトの作り方を見ながら製作。
リップは、三角定規の無地の部分を使用。
塗装はMrカラーの筆塗りで、アイのワイヤーは鉄製の針金を使用。
コーティングは水性ニス。(かなり劣悪な仕上がり)
.
<第二期>
社会に出てすぐの頃、泉和磨氏のハンクルに感銘を受け、ホイル貼りを始める。
このころは全て、ラパラのコピーだった。
コーティングはクリアラッカー。(見た目は上々だが強度に難あり』
.
<第三期>
20代後半、遠藤氏のウッドベイトに深く感動し、バルサではあるものの、
超リアル系ミノーの製作にハマる。尚、遠藤氏はアガチスを使用。
※アガチス⇒鉛筆に使われる木材で加工性に優れる。
但しアクションについては二の次で、
販売すれば『見かけ倒し』の誹りは免れまい。
コーティングはセルロースを使用。(見た目は一流だがアクションは三流)
.
<その後>
フライにハマり、ルアー製作に充てるべき時間は全てフライタイイングに。
ボトルシップで鍛えた手先を駆使した仕上がりには自信があったのだが、
釣友の極めて雑なフライに釣り負け、迷路に突入する。
※外観よりも流し方が重要だとフライを休止してから気付く。
.
<現在>
しげるさんの、実用性を重視したルアーを見て、
改めて、ルアーは兵器なんだと再確認する。
兵器に求められるのはファッショナブルな外観ではなく、
ターゲットを射止める性能のみであることを再確認。
戦闘機など、性能を追求すれば自ずと格好良くはなるものの、
格好の良さが即ち性能ではないのは当然である。
※しげるさんのルアーが格好悪いと言ってる訳ではないですよ。
試作に費やす時間の分配を、
アクションなどの性能に振り分けるべきってことなんです。
ヘルクライマーさんのハンドメイド歴、長いですね!
中学生時代のリップは三角定規の無地の部分を使用というのが創意工夫の素敵なところだと思います!
ハンクルとウッドベイト!ハンドメイドミノーのレジェントですね!
ルアーもフライも作られてますし、ヘルクライマーさんは器用な方だと思います(^^)
僕は小学生の時に図画工作で1をとったような字も絵も下手の筋金入りの不器用なので、見た目については技術的に限界があるだけです(^_^;)
試作に費やす時間の配分はアクションなどの性能という部分は共感します!(^^)!
Guten Abend!
写真で拝見する限りでは、図画工作1の出来栄えではないですよ。
授業態度が悪かったんじゃないですか?(笑)
.
ただねぇ、ルアーもフライも、
見た目を追及する程に釣果は遠ざかるんですよね。
特にフライですが、昆虫標本さながらの仕上がりのものが、
MSCと呼ばれる、毛をフワっと巻いただけのものに
釣り負けるなんてのはザラなんですよ。
.
後日、フライの雑誌の記事を見て納得。
『どの程度、リアルさを求めるべきか』の追求で、
動きを伴わないリアルさは、弊害でしかないと断言しています。
魚は、流下する昆虫(フライ)の足が6本であるか、
ニンフのテイルが3本であるかなんてことは見ていないと。
.
ルアーも恐らく同様でしょう。
シーバスでの話しですが、サヨリの標本みたいなリアルミノーが一時出回り、
多くのアングラーが飛びついたのですが、
残念ながら見かけ倒しで終わりました。
ボートシーバスにおいて、
サヨリへのボイルにこのルアーを投げた同行者は全く釣れず、
スミスの『ハルカ125S』を投げた自分の独壇場でした。
※このときのハルカ125Sは、パールホワイト&背面は蛍光グリーンで、
サヨリとは似ても似付かぬ外観です。
.
結局、アクション(動き)を蔑ろにしてまで、
外観を追求すべきではないと言うことでしょうね。
.
<追記>
いよいよシーズンは終盤を迎えました。
お互い、悔いの残らない良い釣りを楽しみましょう。
※数だけは一丁前で、
尺物2本の目標は未達成に終わるヘッポコアングラーの戯言でした。
授業態度が悪くないのに図画工作1なので生粋の不器用なのです(^_^;)
リアルさより動くについてはすごく共感します。
リアルな方が釣れるなら、不器用な僕はルアー作りは続けていないので(^^)
人間はリアルの方が釣れるかもしれませんが、渓魚はリアルが釣れる訳ではないと思います。
ただ、器用でリアルな見た目を作れる方は内部構造も不器用よりは上手だとは思います(>_<) 『ハルカ125S』のお話しは人が使っているのと違うルアーを投げるのも釣果のポイントという教訓かもしれませんね! 今シーズン、残り少なくなりましたね。 お互いに怪我なく楽しみましょう(*^^)v